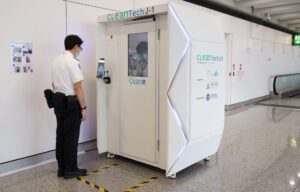香港の税制はシンプルかつ低税率
香港の税金に係る執行機関はInland Revenue Department(IRD:税務局)になり、税制は日本に比べ、シンプルかつ低税率です。また源泉地主義を採用しているので、香港を源泉とする所得にしか課税されません。香港でよく耳にする「オフショア所得」は香港外を所得の源泉するため、香港で課税されないのです。これは日本・アメリカ・オーストラリアといった国々が採用する居住地主義(つまりその国の税務上の居住者は、全世界所得が課税対象)とは対極の方式です。
その他、香港では相続税、配当課税、消費税または付加価値税、日本の住民税・事業税のような地方税がないのも特徴です。
所得に対する税と税率
香港における所得に課税される主な税金は、①事業所得税(Profits Tax) ②給与所得税(Salaries Tax) ③不動産所得税(Property Tax)の3種類になります。
事業所得税(Profits Tax)
事業所得税は、法人、個人事業主、パートナーシップ等から稼得される所得の内、香港源泉の所得に課税される税金で、繰越欠損金は、原則として永久に繰り延べることができます。法人の事業所得税は、経営者の国籍を問わず、香港の中で行われた経済活動および香港での貿易取引の収益が課税の対象です。
2018年4月以降の課税年度において2段階の税率措置が導入されました。法人事業主については、利益のうち200万香港ドルまでは8.25%の税率(従来は16.5%)、200万香港ドルを超える利益については、従来通り16.5%の税率で課税されます。非法人事業主(個人事業主、パートナーシップ)については、200万香港ドルまでは7.5%の税率(従来は15%)、200万香港ドルを超える部分は従来どおり15%の税率にて課税されます。
200万香港ドル以下の利益に対する利得税率の半減措置により、法人事業主は最大で16万5,000香港ドル、非法人事業主は最大で15万香港ドルが減税されることとなります。
なお、グループ会社がある場合は、グループ内の会社のうち1社のみが軽減税率を享受できます。
給与所得税(Salaries Tax)
給与所得税は個人の給与に課税される税金です。こちらも事業所得税同様、香港外源泉の給与所得は非課税になります。コミッション、賞与、チップ、手当、その他臨時収入、香港で提供されたサービスに対する収入および年金も課税対象に含まれます。
2018/19年度の税率は課税所得の15%の標準課税方式もしくは累進課税方式(段階的な2~17%の累進税率)により算定された税額のいずれか低い方が適用されます。ちなみに独身の方で、15%の標準税率による税額の方が低くなるのは、課税所得がおよそ170万香港ドル以上の場合になります。そのため給与所得税対象者の内、わずか1.7%しか標準課税方式の対象になっていません。
その他、広範な控除と減税により香港の給与所得者のおよそ半数は給与所得税がゼロになっています。
不動産所得税(Property Tax)
不動産所得税は香港内不動産の賃貸収入(所得)の80%に対して15%の標準税率で課税される税金になります。一方、法人の不動産賃貸収入は不動産所得税の対象とならず、事業所得税として課税されます。
上記2所得と同様に、香港外の不動産からの賃貸収入はオフショア所得になり非課税になります。
税金申告の実務
賦課納税
日本のような申告納税制度ではなく、賦課納税制度を採用しています。納税者は課税所得及び税額を自ら計算し税務申告書に記載して提出します。その後IRDは課税所得を査定し、税額を賦課通知書にて通知します。
課税年度
香港では4月1日から翌年3月31日までが課税年度となります。法人の場合は課税年度内に終了する各法人の事業年度がそのまま採用されます。つまり2019年12月31日が期末日である場合、課税年度は2019年1月1日~2019年12月31日になります。課税年度終了後にIRDから発行される税務申告書に必要事項を記入し、所定の期間内にIRDへ提出しなければなりません。IRDはその税務申告書に基づき、査定を行い賦課決定通知書を発行し、異議がなければ、指定された期限内に税金を納付します。
予納とホールドオーバー制度
税金を納付する際は、確定年度分の納税に合わせて、翌年度分の予納も行います。これは翌年の税収を予め確保することを目的をしており、通常は確定年度分と同額が予納分として賦課されます。しかし予め翌年度の課税対象所得が確定年度の90%未満である事が見込まれる等を根拠に予納額の減額を申請することが可能です(ホールドオーバー制度)。
]]>